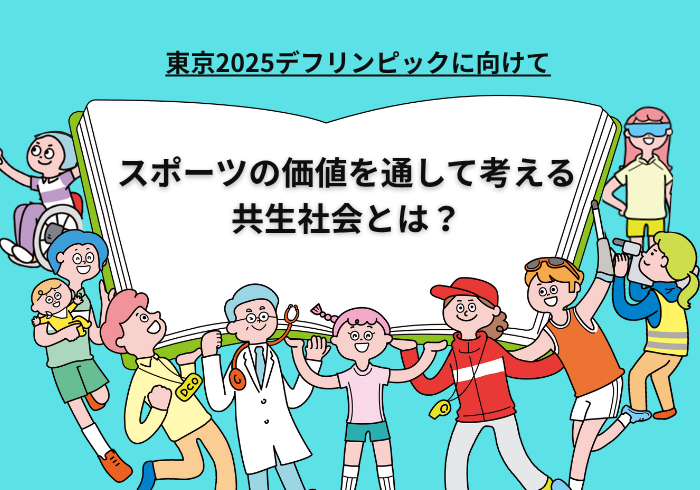NEWS & TOPICS
ニュース&トピックス
2025.11.11
《東京2025デフリンピックに向けて》スポーツの価値を通して考える共生社会とは?
東京2025デフリンピックが間もなく開催されます!
デフリンピックとは、聴覚に障がいのあるアスリートが参加する国際大会で、「デフ(deaf:耳の聞こえない)」+「オリンピック」=デフリンピックからなり、オリンピックやパラリンピックと同様に4年に1度、夏季大会と冬季大会が2年ごとに交互に開催されます。
東京2025デフリンピックは、100周年の記念すべき大会であり、日本では初めての開催になります。
大会サイト
https://deaflympics2025-games.jp/#gsc.tab=0
東京2025デフリンピックでは3つの大会ビジョンを掲げています。
- デフスポーツの魅力や価値を伝え人々や社会とつなぐ
- 世界に、そして未来につながる大会へ
- "誰もが個性を活かし力を発揮できる"共生社会の実現
参照
https://deaflympics2025-games.jp/main-info/about/#gsc.tab=0
障がいの有無や人種・国籍に関わらず、全ての人が楽しくスポーツをする、見る、支える、応援すること、そしてスポーツを通した共生社会の実現について、「スポーツの価値」をキーワードに今回は一緒に考えていきましょう。
スポーツの価値を通して、誰もが自分らしく生きられる社会(共生社会)を実現するために、私たち一人ひとりはどのようなことができるでしょうか?
スポーツのいいところやスポーツが社会や人等に対して与える良い影響を「スポーツの価値」と呼びます。スポーツにはどのような「価値」があるでしょうか?
クリーンスポーツ・アスリートサイトのクリーンスポーツに関する原則及び価値のページでは、スポーツの価値の例として次のようなものを挙げています。
- 勝利を目指して努力すること、勇気を持って挑戦すること。
- チームメイトや対戦相手をリスペクトし、自身の最大限の力を発揮し、試合を楽しむこと。
- スポーツを通して国境、年齢や人種を越えた他者を理解する心を育むこと。
- スポーツを通して人々の心を動かし、社会のリーダーとなっていくこと。
スポーツの価値は、人それぞれに異なる多様なもので、どれもが大切なものです。
多様性を認め合う
スポーツの価値は人それぞれに多様なものですが、それぞれの価値は競技、国、障がいの有無によって差があるものではなく、世界の誰とでも共有し合うことができます。
社会において、国籍、年齢、性別、また障がいの有無に関係なく混ざり合っている状態を「多様性」と言いますが、人は一人一人が異なり、目に見える違いもあれば、目に見えない違いもあります。その違いを認識し、その違いを理解する、認め合う努力は、共生社会の実現にはとても重要です。
スポーツは「スポーツの価値」をキーワードにその多様性(違い)を認め合い、理解を促すきっかけになります。
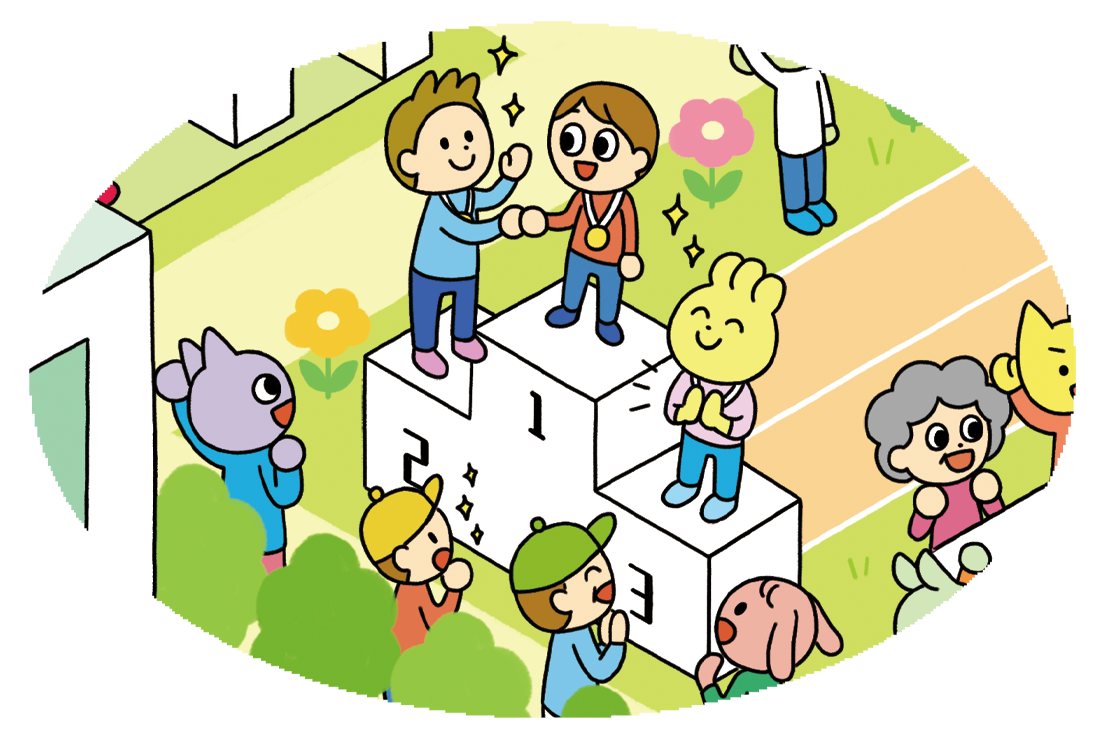
例えば、スポーツを通して相手を尊敬する気持ちや、仲間との友情、試合に挑む勇気やその楽しさなどの「スポーツの価値」は、年齢や障害の有無に関係なくスポーツに参加する全ての人が得ることができますが、何を「スポーツの価値」と感じるかは一人一人異なります。
自身の意見と異なることは、どちらの意見が正しいということではありません。重要なことは、スポーツに参加する全ての人がお互いの良さを受け入れ、多様な中でも同じ空間で様々な感情を共有・共感し、楽しもうとする姿勢です。
「スポーツ」は言わば多様性を認め合うための交流(コミュニケーション)手段の一つです。

スポーツの価値をイメージした文様:PLAY TRUE PLANET Sport & Art
多様性の先にある包摂性を考える
水泳競技のパラリンピアンで、2025年10月1日よりスポーツ庁長官に就任された河合 純一さんは、「(動画)パラリンピアンと考える、スポーツの価値を通した共生社会」の中で、「共生社会の実現には<多様性の先にある、包摂性(インクルージョン)に注目していくことが重要>」と話しています。
※包摂性(インクルージョン):多様性を認め、個々人が尊重され安心して能力を発揮できる環境のこと。
お互いを認め合い、個々人が尊重され誰もが安心して自身の能力の最大限を発揮できる環境であることはスポーツにおいてもとても重要です。
先ほど、スポーツの価値はお互いが違うことを認め合い、相手に共感する姿勢が重要とお伝えしました。
さらに、河合さんは動画の中で、誰もが安心して能力を発揮できる環境づくりとは、ハード面(会場設備など)だけではなく、ソフト面(それぞれの意識や行動)のことも含み、「人々の意識、ソフト面が変わり、行動が起こせるような当たり前の状況が日常になっていく」ことが今後の日本には求められると話しています。
東京2025デフリンピックには70~80か国・地域からアスリートや役員、審判などを含む約6,000人の選手団が参加します。
デフリンピックは、スポーツをする、見る、支える、応援することを通して、お互いの感じるスポーツの価値の違い(多様性)を共有し、認め合うこと、そしてその先にある、誰もが安心して自分らしく能力を発揮できる環境づくり(包摂性)に対する意識や行動として、私たち一人ひとりができることを考えるきっかけにできるのではないかと思います。
日本で初めて開催される東京2025デフリンピックが皆さんにとって、スポーツをする・見る・支える・応援する立場や国や年齢などを超えて、多くの方とスポーツの価値と多様性を共有し合い、より良い社会の実現に繋がる機会となりますように!